
おはようございます。
夏の甲子園で沖縄県代表の沖縄尚学高校が敗戦。
夏が終わった感じのする週明けですね。深天舎です。
二十四節気でも立秋を過ぎ処暑を控えているので暑中見舞いでは非常識、ということになります。
ここは否が応でも、残暑が厳しいざんしょ、などの20世紀に使い古されたダジャレを21世紀(2023年)に持ち込み、冷ややかな笑いで残暑を乗り切りたいものです(意味不明)。
さて。
今日は久しぶりにまともなテーマ「利益」についてのお話です。
旧知の方から連絡を頂き、営業的なお悩み解決策について相談されました。
実によくある話なのですが、
利益率と利益額、どちらが優先?
という悩みです。
経営者の皆様なら全員が”利益額”とお答えになるこの問題、現場でも無論のこと”利益額”が正解となるわけですが、実際には「利益率を向上させたい」という標語が掲げられていることもあります。
A:利益額は少なかったが、利益率は高かった。
B:利益率は低かったが、利益額は大きかった。
上記ふたつのシチュエーションのうち、自社であってほしいのはどちらでしょうか。
もちろん、Bですよね。
利益率と利益額、優先して考えるべきは利益額です。
しかし、利益額の少ない仕事でも受注する必要があるときに、ある程度利益の目安が必要となる。それが利益率の使い方のひとつです。
たとえば銀行で借り入れをするとき、少額の借り入れほど金利が高くなる。多額の借り入れになると、金利が低くなる。借りる側からすれば少額なんだから金利は下げてよと言いたくなるところですが、むしろ貸す側からすると少額の借り入れからでも一定ラインの利ザヤは得なければならないし、逆に多く借り入れてもらえるなら率を下げても十分な利ザヤが得られるので金利は下げられる。
金融機関だって、少額借り入れは利益が少ないのであまり取り扱いたくはないのですが、だからといって大切なお客様のご依頼をお断りすることなど有り得ない選択肢です。ならば、お互いの落としどころとして少し高めの金利を設定するわけです。
いわゆる”スケールメリット”と言って古くから使われている常識的な考え方ですが、これがしかし、未だによく理解できずにいる方も少なくない。
ご相談頂いたのは、利益率と利益額についてどうにか改善したい、というお悩みでございました。
こんなときの最適解はただひとつ。
利益率と利益額の関係性について、きっちりと線を引くことから始めましょう。
優先すべきは利益額、常に利益率を気にしながらも、優先するのは利益額。そういうことをひとつひとつ丁寧に根気よく説いていく。
それが改善までの最短距離です。
じゃあ、利益率を向上させよう! などの標語はなんで必要なんだよ!
と言いたい方。
利益率向上の標語は必要かつ重要な存在です。
ただ、表現は考え直したほうがいいですね。
よく会議などでは「我が社の利益率が1%向上したら、利益が〇〇円アップする。」と説明されるのですが、そういう表現ではあまりピンとこない社員も少なくないです。
そこで「我が社の利益率を1%改善できたら、社員全員の月給を1%アップさせることもできる。」とお伝えすれば、率を上げることの大切さも理解しやすくなります。
全社的な利益の向上は、全社員の努力によって得られるものですから、全社員の意識を利益向上に向けるようにハッキリと伝える。
そんなときにはケースバイケースとなる利益額より、目安として分かりやすい利益率を使う、ということなのですね。
実際のところ、全社的に利益率を1%向上できたら、社員の給与は2%アップなんてこともできたりします。ただ、実際にそれ(給与アップ)をやるかどうかはまた別問題なので、揉めたり揉めなかったりするのですが。
こうやって考えてみると、会社経営って、面白いものかもしれません。←何を今さら。苦笑
いやはや、残暑が厳しいざんしょ。
でも今日も頑張ってまいりましょう。笑


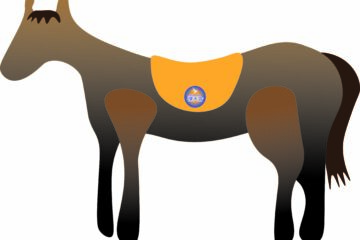
0件のコメント