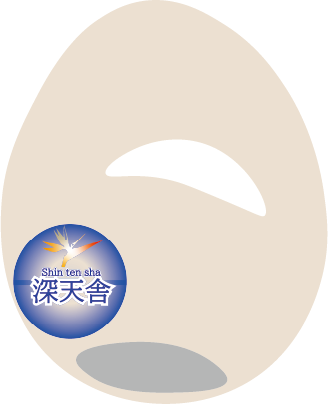
おはようございます。
雨上がりの朝、さわやかとは言い難いですが今は雨一滴も有り難いですね。深天舎です。
2024年2月29日。
今日で2月も終わり、明日からは3月ですね。
ひょうえー!年度末近し!(;゚Д゚)
また決算作業がやってくるのね。え? 早くね? あれから1年が経つわけ? 的な焦りを抱えている深天舎です。(*´Д`*)
さてさて。
学校給食に提供されたうずらの卵をのどに詰まらせた児童が死亡するという痛ましい事故が起きました。
これを受けて全国の自治体ではすぐに対策を講じました。
当面、給食からうずらの卵を除外する自治体もあるそうです。
え?うずらの卵を除外?( ゚Д゚)ポカーン
それは解決策としては早計に失する、ですね。
うずらの卵がのどに詰まったから、うずらの卵をやめる。となると、似たような形状の食材も(先回りして)取り止めたほうが良いのではないか、と考えてしまいそうです。
そうではない。給食の栄養を考慮しても、またうずらの卵の生産者の経済を考慮しても、ここはうずらの卵を除外するというような単直な施策ではいけません。
いくつかの自治体では実施していますが、児童生徒にうずらの卵をよく噛んで食べることを教えたという施策がありました。
これは良い解決策ですね。
そしてもうひとつ、これは実際に取材しましたが、現在の小学校では昼休みや給食時間がかなり短く設定されているそうです。
給食を食べた後に掃除をするので、昼休みはほとんどない学校もあるそうです。
もし、給食時間を短く設定しているのであれば、
急いで食べさせない(給食時間を延ばす)。
という解決策の方向性もあるでしょう。
事故の直接的な原因だけではなく、環境要因も丁寧に見渡していくことが大切ですね。
学校の先生方、求められることが多すぎて大変だと思います。
昔のように大声出したら問題になりますし、ビンタなんてトンデモナイですよね。
受難の時代になってきたのかな、と思います。お察し申し上げます。
また、お亡くなりになった児童の御冥福を心よりお祈り申し上げます。



0件のコメント